May the Force be with you. ― 2012/10/31
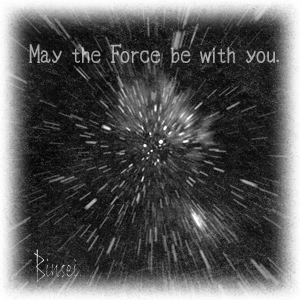
先月に引き続き、
またまた健康に関することでも書こうと
何気なくニュースを眺めていると、
ディズニーがルーカスフィルムを買収とか。
本来9部作と言われていたスターウォーズの
エピソード7以降が映画化されるらしい。
以前ジョージ・ルーカスは
7以降のシリーズは作らないと発言していたし、
もともと構想のあったストーリーアイデアは、
すでに1~3の中に吸収されたとの噂もある。
またその後に色々な作者によって生み出された
スピンオフ作品などがありややこしい。
世界中にコアなファンが存在し、サーガともいわれる作品の続編となれば、いろいろ論議を呼ぶだろう。
しかし私は新しい作品が生み出されるのなら、単純に楽しみである。
年がバレてしまうが、最初の作品エピソード4が日本で公開された時、
親戚の女の子と劇場に観に行った思い出が、セピア色に浮かび上がってくるのだ。
この、親戚の女の子と行ったというあたり、全然色気のないしょぼいエピソード1なのだが、
映画自体は当時の映像技術を遥かに凌駕したエキサイティングな作品として、強烈な印象を受けたものだ。
今となっては初期の作品の特殊効果もやや陳腐なものになってしまい、
後に製作されたエピソード1〜3の宇宙船のシステムの方が、
時代的に後の4〜6のものより遥かに優れているという矛盾もあるが、まあこれはご愛嬌。
当時、ミレニアム・ファルコン号が光速に突入する時のエフェクトに
テンションが上がったのは私だけではあるまい。
現実的には光速に近い速度で移動しようとすれば、星はあのように後方に軌跡を残しながら過ぎ去らない。
むしろ降雨現象により、前方に集束するように集まり、ドップラー効果で虹色に輝くはずである。
ま、そんな事を言い出すのは野暮というものだな。
新作が公開されれば、映画館に足を運ぶことになるだろう。また一つセピア色の思い出が増える訳だ。
私の座骨神経が上映時間に耐えられればの話だが。…おっと、またしてもジジ臭い話になってしまった。
フォースと共にあらんことを。
またまた健康に関することでも書こうと
何気なくニュースを眺めていると、
ディズニーがルーカスフィルムを買収とか。
本来9部作と言われていたスターウォーズの
エピソード7以降が映画化されるらしい。
以前ジョージ・ルーカスは
7以降のシリーズは作らないと発言していたし、
もともと構想のあったストーリーアイデアは、
すでに1~3の中に吸収されたとの噂もある。
またその後に色々な作者によって生み出された
スピンオフ作品などがありややこしい。
世界中にコアなファンが存在し、サーガともいわれる作品の続編となれば、いろいろ論議を呼ぶだろう。
しかし私は新しい作品が生み出されるのなら、単純に楽しみである。
年がバレてしまうが、最初の作品エピソード4が日本で公開された時、
親戚の女の子と劇場に観に行った思い出が、セピア色に浮かび上がってくるのだ。
この、親戚の女の子と行ったというあたり、全然色気のないしょぼいエピソード1なのだが、
映画自体は当時の映像技術を遥かに凌駕したエキサイティングな作品として、強烈な印象を受けたものだ。
今となっては初期の作品の特殊効果もやや陳腐なものになってしまい、
後に製作されたエピソード1〜3の宇宙船のシステムの方が、
時代的に後の4〜6のものより遥かに優れているという矛盾もあるが、まあこれはご愛嬌。
当時、ミレニアム・ファルコン号が光速に突入する時のエフェクトに
テンションが上がったのは私だけではあるまい。
現実的には光速に近い速度で移動しようとすれば、星はあのように後方に軌跡を残しながら過ぎ去らない。
むしろ降雨現象により、前方に集束するように集まり、ドップラー効果で虹色に輝くはずである。
ま、そんな事を言い出すのは野暮というものだな。
新作が公開されれば、映画館に足を運ぶことになるだろう。また一つセピア色の思い出が増える訳だ。
私の座骨神経が上映時間に耐えられればの話だが。…おっと、またしてもジジ臭い話になってしまった。
フォースと共にあらんことを。
怨霊となって蘇るほど恨みはない。 ― 2012/03/25

少し前だが、珍しく歌舞伎を観に行った。
中村吉右衛門の「俊寛」である。
懇意にしている取引先の営業の人が
チケットが手に入ったからと誘われたのだ。
しかも前から5列目の真ん中あたりの良い席で、
久しぶりに生の芝居を堪能した。
さすがに吉右衛門の俊寛は素晴らしく、
最後の最後まで、まさに円熟の至芸であろう。
歌六の瀬尾も芝居っ気たっぷりで楽しめた。
又五郎と歌昇の襲名披露に続いて上演された
「船弁慶」もなかなか。
テレビなどで観れば、知盛の霊が出るまでは
眠くなってしまうところだが、
キレのある囃子も含め、生の舞台の迫力の前では寝るどころではない。
と、まあ、楽しい観劇であった。
…あの女さえいなければ。
その女は幕が開いてからやってきて、我々の前でウロウロした挙句、私のその連れの隣に座った。
葬式帰りのような全身黒づくめで、どうやら40代のよう。
身を乗り出すようにしてすぐ芝居に集中し始めたので、熱心なファンくらいに思っていた。
しかしどうもおかしい。「えらい!」とか「しっかりせえ!」とか妙な声をかける。
確かに芝居の内容には沿っているのだが、歌舞伎のかけ声というのはそういうものではない。
歌舞伎は芝居というよりは、芝居っぷりを観るといってもいいのである。
だからこそよく心得た観客が見せ場で「播磨屋!」などと屋号で声をかけるのだ。
廻りの観客も少しざわめきだして、チラチラ女の方をうかがい始めた。
我々は連れだと思われはしないかヒヤヒヤしていたのだが、どうやらかなり酔っぱらっているようで、
変に窘めると、予想外の反応をしてヘタをすれば芝居を止めてしまう可能性もあったでのある。
休憩時に女に話しかけられた連れは、普段の営業の経験から40代の女性の扱いに自信を持っていたようで、
その行動を制御しようとしたのか、丁寧に応対し始めたのである。
たちの悪い酔っぱらいの女はますます調子に乗って、
差別発言やこういった席には多い上流への批判など、あたりに聞こえるのも構わず言いたい放題で、
解説のレシーバーなど邪道だと、前の席の客をハゲオヤジ呼ばわりとビール片手に暴走の限り。
結局、前列の客たちの通報で、船弁慶の前に係員に連れ出されたのであるが、後味は悪かった。
私には営業の経験はほとんどないが、若い時の飲み歩きで酔っぱらいの対応は心得ている。
変に応対して話し相手になると思われたら、とことん絡まれるのである。
拍子抜けさせるようにスカして、こちらへの興味を失わせるのが一番である。
飲む席で全員がこれをやるといずれキレられるかも知れぬが、観劇とその休憩程度なら大丈夫だろう。
ただ暴走したからこそ途中でつまみ出される事になったので、まわりの観客同様、
おそらく変なかけ声が聞こえていたであろう、吉右衛門や他の役者はホッとしたのではないか。
しかし何が腹が立つといって、その女、連れとの会話で私と親子か?と言っていた事である。
いくら普段から加齢を嘆いているといっても、年下とはいえ不惑を過ぎた男と親子とは。
もっとも病院で母と夫婦に間違えられた兄ほどのショックは無いがね。
中村吉右衛門の「俊寛」である。
懇意にしている取引先の営業の人が
チケットが手に入ったからと誘われたのだ。
しかも前から5列目の真ん中あたりの良い席で、
久しぶりに生の芝居を堪能した。
さすがに吉右衛門の俊寛は素晴らしく、
最後の最後まで、まさに円熟の至芸であろう。
歌六の瀬尾も芝居っ気たっぷりで楽しめた。
又五郎と歌昇の襲名披露に続いて上演された
「船弁慶」もなかなか。
テレビなどで観れば、知盛の霊が出るまでは
眠くなってしまうところだが、
キレのある囃子も含め、生の舞台の迫力の前では寝るどころではない。
と、まあ、楽しい観劇であった。
…あの女さえいなければ。
その女は幕が開いてからやってきて、我々の前でウロウロした挙句、私のその連れの隣に座った。
葬式帰りのような全身黒づくめで、どうやら40代のよう。
身を乗り出すようにしてすぐ芝居に集中し始めたので、熱心なファンくらいに思っていた。
しかしどうもおかしい。「えらい!」とか「しっかりせえ!」とか妙な声をかける。
確かに芝居の内容には沿っているのだが、歌舞伎のかけ声というのはそういうものではない。
歌舞伎は芝居というよりは、芝居っぷりを観るといってもいいのである。
だからこそよく心得た観客が見せ場で「播磨屋!」などと屋号で声をかけるのだ。
廻りの観客も少しざわめきだして、チラチラ女の方をうかがい始めた。
我々は連れだと思われはしないかヒヤヒヤしていたのだが、どうやらかなり酔っぱらっているようで、
変に窘めると、予想外の反応をしてヘタをすれば芝居を止めてしまう可能性もあったでのある。
休憩時に女に話しかけられた連れは、普段の営業の経験から40代の女性の扱いに自信を持っていたようで、
その行動を制御しようとしたのか、丁寧に応対し始めたのである。
たちの悪い酔っぱらいの女はますます調子に乗って、
差別発言やこういった席には多い上流への批判など、あたりに聞こえるのも構わず言いたい放題で、
解説のレシーバーなど邪道だと、前の席の客をハゲオヤジ呼ばわりとビール片手に暴走の限り。
結局、前列の客たちの通報で、船弁慶の前に係員に連れ出されたのであるが、後味は悪かった。
私には営業の経験はほとんどないが、若い時の飲み歩きで酔っぱらいの対応は心得ている。
変に応対して話し相手になると思われたら、とことん絡まれるのである。
拍子抜けさせるようにスカして、こちらへの興味を失わせるのが一番である。
飲む席で全員がこれをやるといずれキレられるかも知れぬが、観劇とその休憩程度なら大丈夫だろう。
ただ暴走したからこそ途中でつまみ出される事になったので、まわりの観客同様、
おそらく変なかけ声が聞こえていたであろう、吉右衛門や他の役者はホッとしたのではないか。
しかし何が腹が立つといって、その女、連れとの会話で私と親子か?と言っていた事である。
いくら普段から加齢を嘆いているといっても、年下とはいえ不惑を過ぎた男と親子とは。
もっとも病院で母と夫婦に間違えられた兄ほどのショックは無いがね。
失笑を巻き起こす道化ならお手の物。 ― 2012/01/31

今年はブログの更新頻度を上げようと考えていたのに
この体たらくである。
もっとも、更新しようにも年明け早々とにかく忙しく、
仮眠、仮眠の連続で、
まともにベッドで寝た日の方が少ないくらいであった。
それもやっと一段落したので、平日ではあったが、
以前無料チケットを入手していたサーカスに、
せっかくなので家族で行ってきた。
市内にこれほどの空き地があったのかと思った広場に、
臨時の駐車場とサーカステントが設けられており、
遠目から否が応でも期待を抱かせる。
開場を待つ列に並んでいると、
入場整理の人の日本語がかなり怪しい。
運営会社はともかく、スタッフやパフォーマーの団員は中国などの外国人が殆どかもしれない。
アクロバティックな演技や、大車輪、バイクパフォーマンス、空中ブランコに道化…。
このサーカス団のレベルがどの程度か、観覧機会の少ない私にはよくわからないが、
休憩をはさんで2時間弱ほどの間、テントの中の非日常空間をまずまず楽しめた。
シルク・ドゥ・ソレイユのような大規模のところはともかく、
このくらいのサーカス団だと、どことなく哀愁があって懐かしい気持ちになる。
実際には出し物に新旧の違いはあるのだろうが、新鮮な驚きよりも郷愁を呼び起こすのだ。
そしてその非日常感は、遠い遠い華やかなものというよりは、
裏町の秘密の場所で、夜な夜な繰り広げられているに違いないと思わせる妖しさがある。
子供の頃に見たチンドン屋や、見世物小屋に通じる、
「すぐ隣にある異世界」とでもいうべき、独特の雰囲気をもっているのではないだろうか。
夜であれば、テントを出ると黒猫に導かれて不思議の国に迷い込んでしまうかもしれない、
そんなおとぎ話を信じたくなる時間でもあった。
と、まあ、タダ券で行っただけのイベントに、もっともらしい事を書いているが、
実際は熱々のたこ焼きをハフハフ頬張りながら、能天気に眺めていたのは、家族しか知らないはず。
この体たらくである。
もっとも、更新しようにも年明け早々とにかく忙しく、
仮眠、仮眠の連続で、
まともにベッドで寝た日の方が少ないくらいであった。
それもやっと一段落したので、平日ではあったが、
以前無料チケットを入手していたサーカスに、
せっかくなので家族で行ってきた。
市内にこれほどの空き地があったのかと思った広場に、
臨時の駐車場とサーカステントが設けられており、
遠目から否が応でも期待を抱かせる。
開場を待つ列に並んでいると、
入場整理の人の日本語がかなり怪しい。
運営会社はともかく、スタッフやパフォーマーの団員は中国などの外国人が殆どかもしれない。
アクロバティックな演技や、大車輪、バイクパフォーマンス、空中ブランコに道化…。
このサーカス団のレベルがどの程度か、観覧機会の少ない私にはよくわからないが、
休憩をはさんで2時間弱ほどの間、テントの中の非日常空間をまずまず楽しめた。
シルク・ドゥ・ソレイユのような大規模のところはともかく、
このくらいのサーカス団だと、どことなく哀愁があって懐かしい気持ちになる。
実際には出し物に新旧の違いはあるのだろうが、新鮮な驚きよりも郷愁を呼び起こすのだ。
そしてその非日常感は、遠い遠い華やかなものというよりは、
裏町の秘密の場所で、夜な夜な繰り広げられているに違いないと思わせる妖しさがある。
子供の頃に見たチンドン屋や、見世物小屋に通じる、
「すぐ隣にある異世界」とでもいうべき、独特の雰囲気をもっているのではないだろうか。
夜であれば、テントを出ると黒猫に導かれて不思議の国に迷い込んでしまうかもしれない、
そんなおとぎ話を信じたくなる時間でもあった。
と、まあ、タダ券で行っただけのイベントに、もっともらしい事を書いているが、
実際は熱々のたこ焼きをハフハフ頬張りながら、能天気に眺めていたのは、家族しか知らないはず。
風が吹けば桶屋が儲かる話、ではない。 ― 2010/11/21

ここを備忘録だということを忘れていた。
見た事を覚えているうちに書き留めておかないと、
くたびれた脳神経回路の迷宮に埋もれてしまう。
というわけで前回に引き続き、映画の話である。
「2012」(2009年)
作品的にはここ20年ほどで沢山作られた、
世紀末・人類滅亡映画の平凡な一つ。
前半の大地が崩壊していく映像が
一種の快感を与えてくれるので、
その部分だけは映画館で見たかった。
だがプロットはともかく、ご都合主義の脚本がひどい。
CGにかけた予算の一部でも脚本に回して欲しかった。
「アリス・イン・ワンダーランド」(2010年)
不思議の国のアリスの続編という体裁をとった作品。
ストーリー的には目新しいものはなく、主人公の成長の表現もとってつけたようだ。
原作にあった、おもちゃ箱をひっくり返したような楽しさもそれほど感じられず、印象は薄い。
「バタフライ・エフェクト」(2004年)
以前から観たかったこの映画を観るついでに、今回集中的に映画鑑賞したという作品である。
ある場所で起きた蝶の羽ばたきが、地球の裏側で竜巻を起こすという、カオス理論によるバタフライ効果。
それにヒントを得て、タイムスリップによって引き起こされる、主人公と周囲の変化を描いている。
本来の意味でのバタフライ効果はこのような事を指していないかも知れないが、
練り上げた脚本で、なかなか他では味わえないテイストの緊迫したサスペンスとなっている。
誰しも、もしあの時に帰って違う選択、別な行動をしたら、
よりよい現在が、あるいは違った人生を送れたのではないかと考えた事があるだろう。
しかし、その選択が必ずしも意図した素晴らしい未来(現在)につながるとは限らない。
ところで、今回いわゆる洋画ばかり観たのであるが、唯一邦画(?)アニメも借りてみた。
おなじみカナバングラフィックスの「ウサビッチ シーズン3」である。
ネットでもシーズン1〜2は公開されているし、有名なシリーズなのでご存知の方も多いだろう。
家族にはこれが一番ウケた。まあ、私の家族である、ある程度予想したことではあった。
AppleがiTunesで映画の配信を始めた。これからはこれで観る事になると思う。
自転車こいでTSUTAYAに行かなくてすむし、延滞の心配も無い。
いよいよ運動不足が加速するというものだ。…このままでは来年の運動会も危うい。
見た事を覚えているうちに書き留めておかないと、
くたびれた脳神経回路の迷宮に埋もれてしまう。
というわけで前回に引き続き、映画の話である。
「2012」(2009年)
作品的にはここ20年ほどで沢山作られた、
世紀末・人類滅亡映画の平凡な一つ。
前半の大地が崩壊していく映像が
一種の快感を与えてくれるので、
その部分だけは映画館で見たかった。
だがプロットはともかく、ご都合主義の脚本がひどい。
CGにかけた予算の一部でも脚本に回して欲しかった。
「アリス・イン・ワンダーランド」(2010年)
不思議の国のアリスの続編という体裁をとった作品。
ストーリー的には目新しいものはなく、主人公の成長の表現もとってつけたようだ。
原作にあった、おもちゃ箱をひっくり返したような楽しさもそれほど感じられず、印象は薄い。
「バタフライ・エフェクト」(2004年)
以前から観たかったこの映画を観るついでに、今回集中的に映画鑑賞したという作品である。
ある場所で起きた蝶の羽ばたきが、地球の裏側で竜巻を起こすという、カオス理論によるバタフライ効果。
それにヒントを得て、タイムスリップによって引き起こされる、主人公と周囲の変化を描いている。
本来の意味でのバタフライ効果はこのような事を指していないかも知れないが、
練り上げた脚本で、なかなか他では味わえないテイストの緊迫したサスペンスとなっている。
誰しも、もしあの時に帰って違う選択、別な行動をしたら、
よりよい現在が、あるいは違った人生を送れたのではないかと考えた事があるだろう。
しかし、その選択が必ずしも意図した素晴らしい未来(現在)につながるとは限らない。
ところで、今回いわゆる洋画ばかり観たのであるが、唯一邦画(?)アニメも借りてみた。
おなじみカナバングラフィックスの「ウサビッチ シーズン3」である。
ネットでもシーズン1〜2は公開されているし、有名なシリーズなのでご存知の方も多いだろう。
家族にはこれが一番ウケた。まあ、私の家族である、ある程度予想したことではあった。
AppleがiTunesで映画の配信を始めた。これからはこれで観る事になると思う。
自転車こいでTSUTAYAに行かなくてすむし、延滞の心配も無い。
いよいよ運動不足が加速するというものだ。…このままでは来年の運動会も危うい。
名を馳せるかも知れない男の独り言。 ― 2010/11/20

ふた月ほど前から数週間かけて、
レンタルDVDで十数本の映画を鑑賞していた。
ここ数年ろくに映画館に行けなかったので、
見ておきたかった映画を中心に借りたのだ。
特に映像表現としての映画を
チェックしておきたかったので、
いきおい人間ドラマ的な作品ではなく、
特殊効果を使ったSFやアクション、
カメラワークに凝ったサスペンスなどが中心になる。
シリーズ物の最新作などを除いて、
いくつか簡単な感想を書いてみる。ネタバレ御免。
「クローバー・フィールド/HAKAISHA」(2008年)
普通の市民が手持ちのビデオカメラで、とてつもない破壊者によるパニックを撮影したという設定の、
ドキュメンタリータッチという斬新な手法をとった作品である。なかなか楽しめた。
ただ、リアリティをこの撮影手法に頼ったために、観客に情報が伝わりにくい事、
具体的なシーンは挙げないが、人間の心理と行動の描写にリアリティが欠けた嫌いがあった。
そもそもそんなパニック状態で、報道カメラマンならぬ市民がカメラを回し続けられないだろうというと、
ミもフタもないか。
「第9地区」(2009年)
地球にやって来たエイリアンが隔離地区で暮すという設定のSF。
ストーリーはこの手の映画としてはオリジナリティがあるのだが、
やはりこの作品のエイリアンも、高度な科学技術を持っているわりに知性の高さが感じられない。
万物の霊長として君臨し続けた自分たちのプライドを保持したいがためであろうか。
「カールじいさんの空飛ぶ家」(2009年)
私はもっとほのぼのとした、泣けるアニメかと思っていたのだが、良くも悪くもアメリカ映画である。
そもそも冒険を夢見た少年が、老人になったというだけで、何故ああも偏屈になるのか分からない。
子どものいない老人は子ども嫌いで偏屈、というステレオタイプに縛られすぎではないか。
こうやって眺めると、結果的に映画館に行かなくてもよかった作品ばかりだったような気もするが、
映画館での映画鑑賞の醍醐味は、大画面にあるというより音響システムにあるといっても過言ではない。
家庭で観賞するには、よほどのAVルームでも完備していないかぎり、どうしても音響は寂しい事になる。
もし、お隣と壮絶なバトルを繰り広げる程の度胸と執念が私にあれば、
騒音おじさんとしてワイドショーで名を馳せるかも知れない。そのときはよろしく。
以上PART 1、次回はPART 2をお送りします。アレとアレとアレの3本です。
レンタルDVDで十数本の映画を鑑賞していた。
ここ数年ろくに映画館に行けなかったので、
見ておきたかった映画を中心に借りたのだ。
特に映像表現としての映画を
チェックしておきたかったので、
いきおい人間ドラマ的な作品ではなく、
特殊効果を使ったSFやアクション、
カメラワークに凝ったサスペンスなどが中心になる。
シリーズ物の最新作などを除いて、
いくつか簡単な感想を書いてみる。ネタバレ御免。
「クローバー・フィールド/HAKAISHA」(2008年)
普通の市民が手持ちのビデオカメラで、とてつもない破壊者によるパニックを撮影したという設定の、
ドキュメンタリータッチという斬新な手法をとった作品である。なかなか楽しめた。
ただ、リアリティをこの撮影手法に頼ったために、観客に情報が伝わりにくい事、
具体的なシーンは挙げないが、人間の心理と行動の描写にリアリティが欠けた嫌いがあった。
そもそもそんなパニック状態で、報道カメラマンならぬ市民がカメラを回し続けられないだろうというと、
ミもフタもないか。
「第9地区」(2009年)
地球にやって来たエイリアンが隔離地区で暮すという設定のSF。
ストーリーはこの手の映画としてはオリジナリティがあるのだが、
やはりこの作品のエイリアンも、高度な科学技術を持っているわりに知性の高さが感じられない。
万物の霊長として君臨し続けた自分たちのプライドを保持したいがためであろうか。
「カールじいさんの空飛ぶ家」(2009年)
私はもっとほのぼのとした、泣けるアニメかと思っていたのだが、良くも悪くもアメリカ映画である。
そもそも冒険を夢見た少年が、老人になったというだけで、何故ああも偏屈になるのか分からない。
子どものいない老人は子ども嫌いで偏屈、というステレオタイプに縛られすぎではないか。
こうやって眺めると、結果的に映画館に行かなくてもよかった作品ばかりだったような気もするが、
映画館での映画鑑賞の醍醐味は、大画面にあるというより音響システムにあるといっても過言ではない。
家庭で観賞するには、よほどのAVルームでも完備していないかぎり、どうしても音響は寂しい事になる。
もし、お隣と壮絶なバトルを繰り広げる程の度胸と執念が私にあれば、
騒音おじさんとしてワイドショーで名を馳せるかも知れない。そのときはよろしく。
以上PART 1、次回はPART 2をお送りします。アレとアレとアレの3本です。

最近のコメント